
Columns Archives
コラム
生涯と業績
本シリーズでは廣池千九郎の生涯と業績を、エピソードを交えながら詳しく紹介します(月毎に更新)。

No.50 雲照律師に仏教を学ぶ 明治30年(1897) 【31歳】
上京した廣池は明治期の名僧、雲照(うんしょう)律師を訪ね、仏教について学んでいる。京都在住の頃から仏教に関心を持ち、『古事類苑』編纂を進める上でも、仏教についての理解が必要だと感じていた。律師は、神道・儒教・仏教の思想に一貫する真理をもって国民を教育することを考えていた。廣池は律師の人格を敬慕するだけでなく、思想にも共鳴していた。後年、廣池はモラル・サイエンスの研究の中で世界の諸聖人の思想の比較を試みるが、この姿勢は律師に相通じるものがある。
画像は雲照律師
No.49 編纂事業参画の意義 明治29年(1896) 【30歳】
廣池にとって『古事類苑』編纂事業に参画した意義は大きかった。まず、専門学に対する実力を養成する機会となった。多くの文献を読み込み、原稿の執筆と編纂によって、研究手段を徹底的に磨いた。手掛けた原稿のメモには「法制史へ」「皇室史へ」などという書き込みがある。専門学の研究に有益な情報を収集し、仕事と同時にその進捗をはかった。次に、経済的に安定したことである。多額の原稿料は図書や資料の購入にあてられ、研究がさらに進展した。そして、師や多くの同僚との出会いがあった。この交流は廣池の学究生活に指針を示し、後の生き方に影響を与える機会となったのである。
No.48 編纂員の仕事 廣池の貢献
『古事類苑』は日本の古代から幕末に及ぶあらゆる書籍、図画、古文書などから、主要なものをすべて原文のまま写し取り、これを分類整理して、それぞれの事項の由来、使用例などを明らかにしている。本書は、現在でも日本の歴史・文化を研究する上で基礎的文献として利用されている。
廣池は帝国図書館、東京帝国大学図書館、宮内省図書(ずしょ)寮などに通いつめ、多くの書籍を読破して筆を執った。その仕事ぶりは同僚も認めるところで、1日数十枚の原稿を作成するほどの勢いであった。廣池は30部門のうち「政治部」「宗教部」「文学部」「方技部」「外交部」「神祇部」などを中心に担当し、全巻の4分の1以上を編纂するという業績を残した。
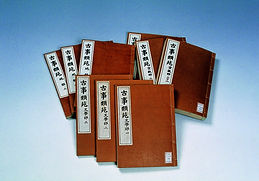
No.47 『古事類苑』の編纂員
『古事類苑』とは、全部で1,000巻、和装本で355冊、洋装本では51冊になる日本最大の百科史料事典である。編纂は明治12年に明治政府の主導で始められ、明治40年に完成した(発行は大正3年)。
明治28年より編修員に就いた廣池は、約13年間にわたってこの国家的事業に貢献している。当時の編修顧問兼校勘は井上頼国、編修長は佐藤誠実(じょうじつ)であった。廣池は2人の指導のもと、業務を通じ、学者としての見識を高めるだけでなく、人間的にも成長する機会を得る。
画像は『古亊類苑』(和装本)。
No.46 『史学普及雑誌』の廃刊と上京 明治28年(1895) 【29歳】
『史学普及雑誌』第8号からは、経費節減のために印刷会社を変更した。以後も、改良を加え、特に第24号からは大改革を行って誌面を一新しようとしたが、ついに時勢には勝てず、明治26年12月には1ヶ月休刊とした。日清の緊張が高まった明治27年4月以降、史学ブームは急速に去り、有力な歴史雑誌が相次いで廃刊に追い込まれた。そして『史学普及雑誌』も第27号を最後に廃刊のやむなきに至った。経営の逼迫もあったが、直接の原因は、廣池が『古事類苑』の編纂のために東京に出たことにある。残務整理を終えた廣池は明治28年5月7日に単身で上京している。

No.45 観光案内ガイドブックの発行 明治28年(1895) 【29歳】
京都における廣池のユニークな活動に『京名所写真図絵』『歴史美術名勝古跡京都案内記』という観光案内ガイドブックの制作がある。この制作は、観光客の便宜をはかって京都市が計画し、廣池が作成したものである。これらには、廣池の純粋な歴史家としての立場が示されている。たとえば、市内を観光する際には「高等の案内者(歴史家として的確な知見を持つ研究者)」を求めなければならないと述べ、廣池自らそれに任じようとしている。
No.44 両親を招いて京都見物 明治28年(1895) 【29歳】
廣池の道徳の核心のひとつに「孝は百行の本なり」がある。「親孝行は全ての行いの基本」という意味で、廣池はこれを母 りえ からよく聞かされて育った。廣池はこの家訓を常に念頭におき、苦しい中でも実践を怠らなかった。珍しい菓子が手に入れば子には与えず、郷里の両親に送ったという。
廣池は『平安通志』の原稿料や寺誌の編纂、古文書の整理の謝礼でまとまった収入があったので生活費などの滞納金を返済し、両親を京都見物に招いた。 両親は2週間ほど滞在し、本願寺詣りや名所旧跡めぐりを満喫した。その間に廣池に『古事類苑』編修員の辞令が届き、一層満足して帰郷したという。

No.43 井上頼国との初対面──『古事類苑』編纂員の抜擢 明治27年(1894) 【28歳】
廣池の元に、国学者井上頼国(いのうえ よりくに)が尋ねてきた。廣池は、中津在住のころから文通によって井上に私淑していた。数時間の論談の末、上京して法制史の研究を大成したい意向を打ち明けた。『中津歴史』『皇室野史』等の著述や『史学普及雑誌』で廣池に注目していた井上は、その意欲と学力を見込んで『古事類苑』の編纂員に推挙した。『古事類苑』とは、明治年間から大正にかけて編纂された、わが国最大の百科史料事典である。この国家的なプロジェクトに廣池は抜擢されたのである。
画像は井上頼国。
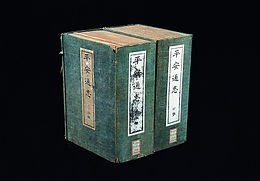
No.42 京都で取り組んだ仕事 明治27年(1894) 【28歳】
廣池は京都において、『史学普及雑誌』の出版と『皇室野史』『日本史学新説』などの著述のほか、観光案内書『京華要誌』の編纂、醍醐寺三宝院の寺誌編纂や比叡山延暦寺の古文書の整理などにたずさわっている。中でも、京都の歴史を記す『平安通志』は歴史的価値が高く、この編纂に関わった意義は大きい。
明治28年は平安遷都からちょうど1100年になるので、平安神宮の創建・博覧会の開催など、この時を期して盛大な祝祭典の行事を催すことになった。これらの事業の一環として『平安通志』の編纂が企画され、官民の歴史家が多数動員された。その1人である廣池は集中して記事の執筆に取りかかった。
画像は『平安通史』

No.41 住吉神社の誓い 明治27年(1894) 【28歳】
明治27年の前半は、清国との対立で、国内は騒然としていた。そのため、売れ行きが悪くなっていた『史学普及雑誌』は、さらに困難に陥っていった。同年7月、廣池は販路拡大のため、炎天下の中、風呂敷に包んだ雑誌を担いで大阪に出向いたが、思うように売れなかった。その帰りに住吉神社(現、住吉大社)の境内で休んでいると、近くの料亭からどんちゃん騒ぎが聞こえてきた。廣池は、昼間から宴に興じる人々と、世のために努力するも報われない自分の状況を比べて、「世の中どこかおかしい」と憤りを覚えた。しかし心を正して住吉神社に参拝し、一層努力する誓いを立てた。
帰宅すると、誓いの効験が現れたかのように、京都市参事会から『平安通志』編纂協力の依頼が来ていた。この仕事の報酬は、貧苦の生活が一転するほどの額であった。
※画像は日記ある誓い(直筆)。内容は「一 国のため、天子のためには生命を失うも厭わず。二親孝心。三 嘘を言わず、正直を旨とす。四 人を愛す。第五 住吉神社のご恩を忘れず参拝」



